こんにちは。私は強度のHSP(繊細さん)です。
大病院の手術室に約4年半勤めましたが、無理がたたって体調を崩し休職中です(休職日記一覧はこちらから)。
休職の間、縁あって生後1か月の子猫を引き取って育てることになりました。
休職するまでの私は仕事の鬼、完全にワーカホリックでした。仕事以外どうでもよかった。
しかし、休職を通して私は自分がHSPであることを深く理解していきました。
そして、仕事をしていない自分には価値がないという強迫観念は薄れていき、自分に合ったゆったりとした生き方や働き方をするのが良いだろうというふうに、考え方が少しずつ変わっていきました。
今回、まだ離乳もしていない子猫を育てるにあたり、改めてそのことを痛感させられる経験をしたので、自戒も込めて書き綴っておきたいと思います。
生後1か月の子猫を迎える

私には半同棲している彼氏がいて、休職中は彼の家にお世話になっています。
その彼が黒色の子猫を貰ってきました。
以前から子猫を飼いたいと話してはいましたが、ある日急に事が進み、トントン拍子でその日のうちに子猫がうちにやってきたのです。
彼の家には先住の人懐っこい猫が一匹おり、私はその子に本当に癒されていました。
子猫の面倒は私がみることになりましたが、先住猫のおかげで猫の素晴らしさを知った私は快諾し、不安もありましたがとても楽しみにしていました。
子猫の親としての責任

うちにやってきた子猫は生まれてちょうど1か月でした。
まだ離乳もしておらず、兄弟猫たちとくっついてふにゃふにゃ眠っていました。
一般的に子猫は、生後2か月頃までは親猫のところで兄弟とともに過ごし、母乳や愛情を貰ったり猫同士のふれあいを通して様々なことを学んだりするのが良いとされています。
今回私たちは見学だけの予定で子猫に会いに行きましたが、保護主さんとの次回のアポイントが難しかったことから急遽その日のうちに譲り受けることになりました。
私は、そのことがとても心に引っかかっていました。
親猫の愛情や、兄弟猫とのふれあいや、学びの機会を人間の都合で奪ってしまったこと。
また、親猫もきっと子猫を探しているだろうと思うと、とても胸が痛かったです。
私がその代わりを務めなければ、そう強く思いました。
初めての子猫育て

彼が飼っている先住猫としばらく暮らしていたとはいえ、その子は出会ったときにはもう大人の猫でしたし、とっても人懐こくいたずらもしない温厚な子でした。
私がやったことは餌をあげることとトイレ掃除と、なでたり遊んだりすることだけ。
しかし、乳飲み子の子猫を育てるにはそうはいきません。
本を読んだりネットで調べたり色々しましたが、不安は尽きませんでした。
季節は冬でしたが、体温調節機能が未熟で低体温になってしまう可能性があると知り、寝ていても心配で何度も目が覚めてしまいました。
ミルクも最初は哺乳瓶からうまく飲めず、排泄もしないのでとても不安でした。
母猫がいればお乳をちゃんと貰えただろうし、体温で温めて貰えて、おしりを舐めて排泄させて貰えていたでしょう。
このころの私は子猫がかわいいと思う余裕は全くなく、死んでしまわないか怖くてたまりませんでした。
唯一、彼が帰ってきて「大丈夫だよ、野生で生きているんだから猫って強いよ」と気楽に構えていてくれたのが救いでした。
また、「こんだけ一生懸命やってるんだから、もし子猫に何かあったとしてもあなたのせいじゃないし、子猫にはきっと伝わってるよ」という言葉も彼から貰いました。
とてもありがたい言葉だったなと思います。
先住猫の心のケア
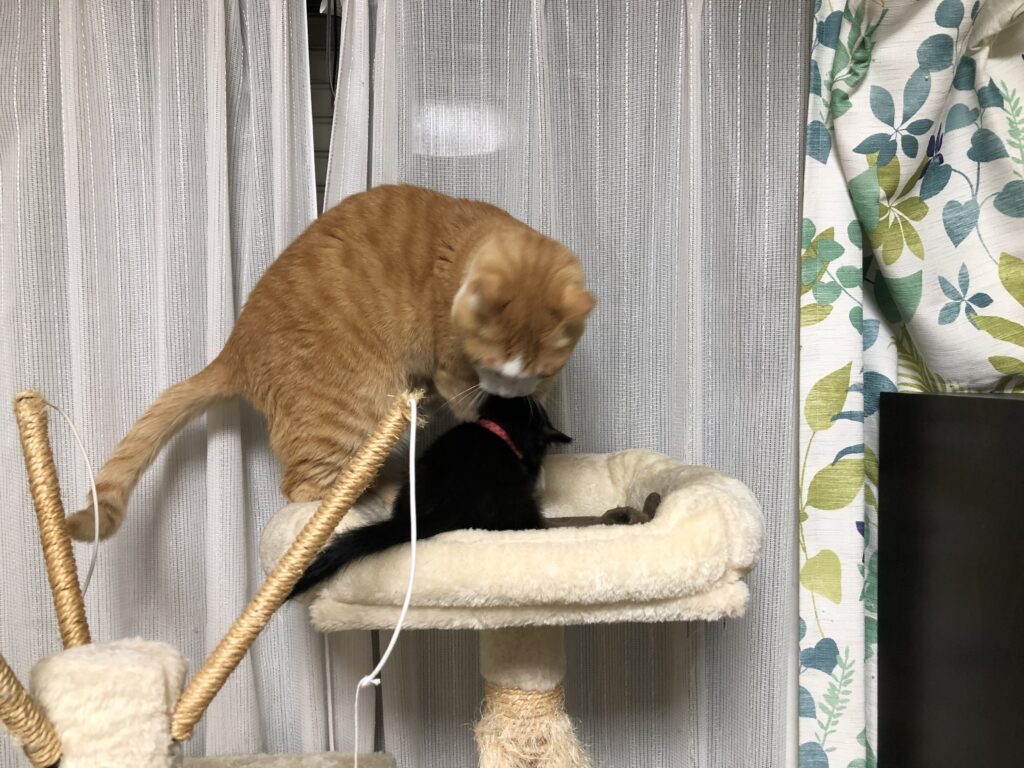
子猫がやってきて、いきなり先住猫と接触させることは推奨されていません。
そのため、最初は部屋を分けて飼っていました。
先住猫は普段主に生活している、エアコンとコタツのあるリビングに。
子猫はエアコンのない二階の部屋にケージを置き、湯たんぽを6時間ごとに替え、電気ストーブで部屋を暖めました。
電気ストーブはエアコンほど性能が良くないため、空気が悪くなったり暑すぎたり時間で切れてしまったりします。
また、まだふにゃふにゃの子猫。新しい環境にひとりぼっちで来たばかりで、誰かがいないと大声でずっと鳴いていて、その声は枯れていました。
寂しくはないか、寒くはないか、体調を崩してはいないだろうか。とても心配でした。
そのため、私は二階で過ごすか、数時間おきに足を運んでいました。
一階のキッチンでは、子猫のためにミルクや離乳食も頻繁に作っていましたが、先住猫はそれを食べたがります。
しかし、肥満でダイエット中のためたくさんあげるわけにはいきません。
そのうち、先住猫は私に近寄らなくなり、自分の餌も食べなくなってしまいました。
先住猫も環境の変化に不安や嫉妬があったのでしょう。
餌を与えるときはずっとなでてあげて、一緒に時間を過ごすようにして、大好きだよと沢山伝えて、それでようやく落ち着き始めました。
対面時は先住猫の威嚇もすごかったのですが、今ではじゃれたりしてくれています。
それでも、まだ寂しそうな様子や拗ねてしまったような様子を見せることがあります。
猫は、とても繊細な生き物なのです。
現在進行形で、先住猫のケアをどうしたらいいか考え続けています。
自分の均衡を崩し始める
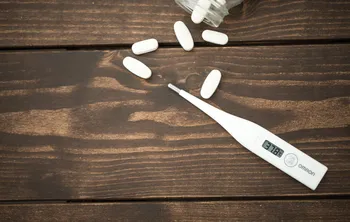
そんな日が続き、私もかなり疲れが溜まってきました。
すると、休職前に出現していた頭痛や胃痛、眼精疲労などが増強し始めたのです。
そのとき、小さな子猫の世話をしながら先住猫のケアをするということは、疑似的に仕事をしていた頃の精神状態を作り出していたことに気づきました。
といってもそんなに大げさなものではありませんが、少し、手術室での状況を思い出させるようなことがありました。
命を預かっていること、常に気を張っていること、相手の状態を気遣ったり、あるいは顔色を伺うこと。また、複数のことを並行してこなさなければならないこと。
家の中で猫二匹の世話をするだけでこれだけ心を揉んでいるわけですから、手術室での4年半は自分にとって相当な負担だったんでしょう。
そのことに、改めて気づくことができました。
無理しない生き方

これくらいのこと、難なくこなしてしまう人は世の中に沢山いるでしょう。というか、そんな人の方が多いかもしれません。
聞いてみたわけでもない猫の心を勝手に想像して、こんなに苦しくなってしまう人も珍しいかもしれません。
以前の自分はそのことに悩んでいました。敏感すぎて生きづらい、考えすぎ、弱いと言われてしまう。
しかし、今では、これは私の長所だと思っています。
猫を育てるという、ある意味では普通のことにおいて、いい意味でも悪い意味でもこれだけ心を動かせる人です。
でも、そんな人は一定数いて、普通じゃないことや生きづらいことに悩んでいるかもしれない。
だからこそ、私は自分が感じたことを発信していきたいと思っています。
今では幸いなことに、猫たちは怒ったり喧嘩したり拗ねたりしながらも、二匹とももりもりご飯を食べて元気に育ってくれています。
優しい彼はそんな私のことを受け入れてくれ、応援し、温かい言葉をかけてくれます。
そんな彼らを見ながら、私は私のまま生きようと思うのです。
無理な環境に身を置いて、感じたことを押し殺して働くことはもうしない。
私は私らしく、自分に合った環境で、自分に合った人に囲まれながら、自分の感じたことを大事にして生きようと思うのです。







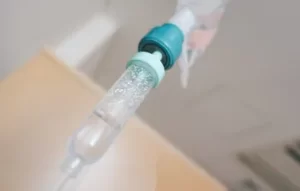

コメント